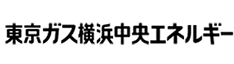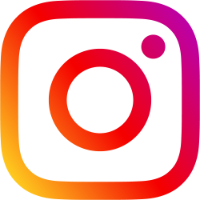NEW
2025.04.21
横浜まち情報
一口サイズの芸術品!カラフルな和菓子が揃う「茶菓 あずきや」

東京ガス横浜中央エネルギー(ヨコエネ)は、横浜市内の8つの行政区(西区・神奈川区・港北区・都筑区・青葉区・旭区・瀬谷区・鶴見区)にて、東京ガスのサービス窓口を担当しております。そこで、日々地域のお客さま先で働く私たちだからこそ知っている、地元のお店情報をご紹介します。
発消費期限は当日、おいしさ重視の和菓子たち
東急田園都市線たまプラーザ駅から徒歩7分。住宅街にさしかかると、赤レンガに白地の垂れ幕が映える和菓子店が見えてきます。「茶菓 あずきや(以下、あずきや)」さんは地元のお客さまに人気のお店。店名には「小豆(あずき)は和菓子の基本だから」と、日々のお菓子作りや接客販売において、常に基本を大切にする想いが込められています。
ショーケースの内外には、おだんご・どら焼き・餅・大福などがぎっしりと並んでいます。

「保存料・防腐剤を一切使っていないので、どうしても日持ちが短くなってしまうんですが……その分おいしさでは他店に負けないように作っています」
そう話すのは、オーナーの水上陽一さんです。お餅の日持ちは当日限り。翌日には固くなってしまうのだそうです。
また、ショーケースにはロールケーキやプリンが並び、「ショコラ羊羹(ようかん)」という創作和菓子まで。一般的な和菓子店とはちょっと違う品揃えです。営業は朝9時からと少し早めですが、筆者が10時前に伺ったところ、入れ替わり立ち替わりお客さまが訪れていました。
聞けば、「駅から成田・羽田空港に向かうバスが出ているため、利用客の方が立ち寄れるように、周辺のお店より1時間早く開店している」とのこと。改めて店内を見回すと、手土産としても喜ばれそうな、華やかでかわいらしい和菓子が目に止まりました。
手土産にもおすすめ!カラフルな看板商品
「あずきや」さんの看板商品の一つは、「茶菓(さか)」という上生菓子です。「生菓子にあまりなじみのない方にも、身近に感じてもらいたい」と、通常の半分サイズで作られています。

「小さいお菓子って、見た目にもかわいらしいじゃないですか。おかげさまで、手土産としても喜ばれています」
近くで見てみると、一つひとつの細工の細かさにびっくり。工程はすべて手作業だそうで、桃の花をモチーフにした茶菓は、グラデーションで見事に美しく色づけされています。一般のお客さまはもちろんですが、茶道の先生もよくご来店になるそうです。
「茶の湯の世界では、お菓子をいただく前に情景を思い描くのだそうです。『このつぼみはあとどのくらいで咲くんだろう』とか、『この鳥はウグイスなんじゃないか』とか。そうした想像力をかき立てられるように、あえて余白を生むようなデザインを意識しています」
いただいてみると、上品な甘さと小さめサイズのせいか、いくつでも食べられそうです。見た目の美しさも相まって、「季節を味わった」という満足感もありました。

もう一つ手土産に人気なのが、「たま最中(もなか)」です。カラフルな一口サイズのまん丸最中は、色ごとに異なる餡(あん)が詰まっています。試しにいちじく餡をいただくと、ねっとりとした食感と同時に、いちじくのさわやかな風味が口いっぱいに広がりました。
さらに、「あずきや」では外せない定番商品が、「生どら焼き」です。開店当初からの人気商品で、一般的なクリームどら焼きと違い、あえてあんこと生クリームを混ぜずに挟んでいます。

「和菓子屋なので、あんこを味わってもらいたいんですよね。しっかり小豆の風味を味わえるよう、ほおばってから初めてクリームと混ざるように仕上げています。……ちょっと手間なんですけどね(笑)」
食べ応えのあるサイズ感ですが、ふわふわ食感のせいかぺろっと食べられます。季節によって「レモンクリーム」や「栗」など、限定商品も販売しているそうです。
ケーキ好きから一転、和菓子職人に
水上さんの実家は、富山県の和菓子屋さん。団子や餅が当たり前にある生活だったせいか、「子どもの頃はケーキの方が好きだった」と言います。
「おやつに決まって和菓子を出されるので、『また団子か……』みたいな感じでしたね(笑)今も洋菓子が大好きで、ホールケーキは一人で1個食べられます」
しかし、大学在学中に京菓子(上生菓子) と出会ったことで、気持ちが一変。繊細で美しい細工に魅了された水上さんは、京菓子作りの名人を訪ね、大学4年から修行を始めることに。しかし、それまでに実家の手伝いでおはぎや餅くらいしか、和菓子作りをしたことはありません。元々細かい作業は得意だったものの、ほぼゼロから技術を学び始めました。
修行は厳しく、最初はあんこを同じグラム数で切る練習から始まりました。まるで寿司職人のようにひたすらあんこを切り、丸くする。師匠に認められないと次のステップに進むことはできず、自分の作った生菓子が店頭に並ぶまで、5年以上かかったそうです。

和菓子作りのなかでも、特に習得が難しかったのが「ぼかし」の技術でした。
「違う色の餡を複数使って、徐々に色が変わるようグラデーションにするんですが……今のように表現できるようになるまで、何年もかかりました」
十数年間で3店舗での修行を経た水上さんは、2007年6月に「あずきや」をオープン。以来、長年にわたって地域のお客さまに愛され続けています。
「昔、顔なじみの常連のお客さまがいたんです。どら焼きが好きで、よく買いにいらしていましたが、ある日ぱったり来なくなってしまって。『どうしたんだろう?』と思っていたら、後日奥様から亡くなったと聞いたんです。
聞けば、最後に召し上がったのが、うちのどら焼きだと言うんです。『もう何も食べられない状態だったのに』と。それが今でも心に残っていて、思い出すたびに『ありがたい』という気持ちと、『もっとがんばろう』という想いが込み上げてくるんです」
その言葉通り、水上さんは毎シーズン新たな商品開発を行っています。特に茶菓はデザインをどんどん変えており、そのときにしか出会えないお菓子ばかりなのだとか。また、洋菓子は「独学で作り方を学んでいる」そうで、次はどんなオリジナル商品が生まれるのか、期待が高まります。
一点物の和菓子で、季節を味わう
4月は見た目にも涼しげな「わらび餅」や、端午(たんご)の節句に向けた「柏餅」が登場します。「こどもの日」を祝うこいのぼりや兜など、一点物の茶菓を楽しみたい方は、事前のご予約がおすすめです。(予約締切などの詳細は、Instagramにてご確認ください)

地域で一番のお店を目指し、日々丁寧にお菓子作りを続けている「あずきや」。ご家族や大切な方への手土産として、あるいは自分へのご褒美として、春の訪れを和菓子で楽しんでみてはいかがでしょうか。
注)当記事でご紹介した商品の価格・サービスは、2025年2月時点のものです。「茶菓 あずきや」さんにインタビューを行い、いただいたコメントを編集して掲載しています。
【店舗情報】

取材・執筆・撮影/弓橋 紗耶
作成:2025年3月